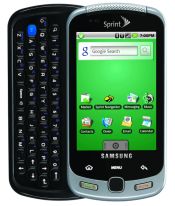韓国の2大検索ポータルサイト「NAVER」と「DAUM」は、2009年にもっとも多く検索されたキーワードを発表した。
NAVERによると、韓国では毎日ポータルサイトを経由して約20億4000万件の検索が行われているそうだ。これはNAVERのサービスが始まった1999年に比べると約200倍も増加した数字だという。テレビのCMでも「ネットで検索!」というナレーションや字幕が必ずといっていいほど入っているだけに、ネットでの検索は重要な情報伝達窓口になっている。
2009年の検索キーワード1位は「新型インフルエンザ」。韓国でも12月15日時点で新型インフルエンザと確診された死者が117人。中には有名芸能人の子供もいた。最初は政府のワクチン確保が遅れ大騒ぎになり休校が相次いだものの、今は全国の小中高校で予防接種が実施され落ち着きを見せ始めている。
2位は世界を驚かせた「ノ・ムヒョン前大統領の死去」。後を追うかのように亡くなった「金大中元大統領の死去」も6位に入った。
3位は大ヒットドラマ韓国版「花より男子」。10から20代の女性の間でシンドロームを巻き起こした。「花より男子」に登場した衣装やアクセサリーが飛ぶように売れ、主人公の別荘があるという設定で紹介された南太平洋のニューカレドニアが憧れのハネムーン名所になった。このドラマの主人公のイ・ミンホをはじめF4は今や大物スター扱いされるようになった。
2008年キーワード1位だったフィギュアスケートの「キム・ヨナ」選手は、2009年4位となった。競技だけに限らず「国民妖精」として、高麗大学入学、メイクやファッション、出演する番組、CM情報、収入に至るまで、彼女に関するありとあらゆることが話題だった。キム・ヨナ選手は3年連続でキーワードベスト10に入っている。
5位は振り付けまで大ヒットしたアイドルグループ「少女時代」の「Gee」。着メロ、着うた、デジタルダウンロードで売り上げ1位となった。どネットでは警察や軍人、男子校学生が「Gee」の振り付けを真似る動画が投稿され、大いににぎわった。
2009年の音楽界は少女グループとワイルドな男性グループが人気を二分した。女性アイドルグループは「2NE1」、「KARA」、「Afterschool」などが音楽チャートを席巻した。健康的でセクシーな魅力持つアイドルが増え、「クルボクジ」(はちみつを塗ったようになめらかで弾力のある太もも)という言葉まで流行ったほど。
日本の草食系男子のように、男性グループも2009年の春までは10代の美少年グループが人気を集めたが、後半は「ジムスンナム」といって、野性的な男性グループに人気が集中した。
その他には、韓国の伝統酒「マッコリ」の検索頻度が例年の2.7倍に増え、順位も大幅上昇した。マッコリはにごり酒のことであるが、韓国の庶民的な伝統酒であるにもかかわらず、日本で先にブームになり、日本向けに色んな種類のマッコリが登場するようになってから、韓国でもマッコリの価値を見直す動きが出始めた。ソウルの繁華街、明洞のデパートでは、のり、キムチに続いてマッコリが売れているほど、人気が急上昇しているという。
「プロ野球」も例年の2倍に上昇した。これはWBCで韓国チームが予想を上回る成績を見せたことで、野球応援の熱気がそのままプロ野球へ流れたからではないかと見られている。
性別による検索キーワードの違いも分析されたが、面白いのは女性よりも男性の方が「ショッピング」というキーワードで検索していること。「ストレス」「憂鬱」を検索したのは女性の方が多かった。
年齢別、地域別にも検索キーワードには差が出ているが、10代が他の世代よりもニュースに登場するキーワードを検索する頻度が高いというから驚いた。「北朝鮮」「大統領」「新型インフルエンザ」など。大学入試の小論文テーマになるので、受験勉強のためだとは思うが、これも意外な発見だった。
季節によっても集中する検索キーワードがあり、年末年始になると「ダイエット」、「初夢」の検索が25%ほど増えるという。「来年こそはダイエット!」、「来年こそはキャリアアップ!」を夢見ながら、検索ばかりで終わってしまわないようにしないと!
(趙 章恩=ITジャーナリスト)
日経パソコン
2009年12月17日
-Original column
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20091216/1021558/