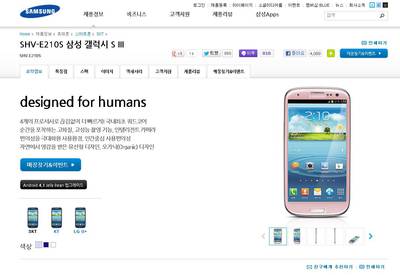.
調査会社ガートナーによると、2012年7~9月、スマートフォンの世界市場は1億6920万台、そのうちサムスン電子のスマートフォンは5500万台、iPhoneは2360万台が売れた。シェアで見るとサムスンが32.5%で世界1位、アップルは14%だった。
人気の端末はサムスンだとGalaxy S3で1800万台、アップルはiPhone 4Sで1620万台売れた。サムスンの躍進によりOSのシェアもAndroidは72.4%、iOSは13.9%と差が広がった。サムスンは携帯電話市場でも世界市場シェア22.9%を記録、ノキアを押しのけて1位になった。
同四半期はアップルがiPhone 5を発売する直前だったため、買い控えするユーザーが多かったこともアップルのシェアが落ちた原因の一つといわれている。しかしアップルとの訴訟をきっかけに、サムスンのスマホがもっと売れるようになったのは確かなようだ。
韓国の複数メディアが米モバイル専門家のコメントを引用して報道していた内容はこうだ。アップルとサムスンが訴訟を始めてから、サムスンのスマホに興味がなかった米ユーザーがニュースを見て、同社のスマホの性能がiPhoneと変わらないことを知り機種変更するケースが増えているという。訴訟をきっかけにサムスンを知ったユーザーもかなりいるそうで、サムスンにとっては一長一短ありの訴訟となった。米国の年末商戦でiPhone 5が爆発的に売れない限り、サムスンがスマホ市場で世界1位をキープし続けるのは間違いないといわれている。
同調査が公開された11月14日、韓国メディアは、「サムスンが部品でアップルを圧迫」「サムスン、アップルと交渉なし」「サムスン、アップルに納品する部品20%値上げ」といった見出しで、サムスンの半導体とディスプレイの部品戦略を報じた。
サムスンと訴訟を始めてからアップルはサムスンの部品を減らしたが、部品の需給に問題がありサムスンに追加で納品するよう要求、これに対しサムスンは20%ほど値上げした価格で納品することにした、という内容だった。サムスンのスマートフォン事業を担当するIT・モバイル担当シン・ジョンギュン社長のコメントも紹介されていて、「アップルとの特許訴訟に関して(HTCのような)交渉はしない」という立場だった。これは、台湾HTCとアップルが11月11日に和解して訴訟を取り下げ、その代わりにライセンス料としてHTCスマホ1台当たり6~8ドルをHTCがアップルに支払うという報道を受けてのものだ。サムスンもアップルと和解するのでは? という予測があったがサムスンは最後まで闘う姿勢を見せた。サムスンは10~12月の実績も7~9月と変わらず世界1位をキープすること間違いないと見ている。
サムスン側は部品の値上げや生産調整に関して、「はっきりしない需要に備えて生産を増やすより、短期的な収益を優先するため半導体(チップ、メモリーなど)とディスプレイの生産を減らす戦略」であり、「アップルを圧迫するため生産を減らすわけではない」とメディアに説明している。
アップルの半導体購入金額は年間270億ドルで、このうち30%ほどをサムスンから購入していた。訴訟の影響で、サムスンにとっては“大口の顧客”を逃したともいえる。しかし、「アップルでなくても納品先はある、安すぎる納品価格を正常価格に戻したので収益改善のきっかけになる」(サムスン)と強気だ。
サムスンが部品を提供しなくなってから部品の需給がうまくいかずiPhone 5の生産量が予定より遅れているというニュースもある。そのせいか、iPhone 5はまだ韓国での発売日が決まっていない。
アップルとサムスンの訴訟はアップルが有利なように見えたが、サムスンの反撃も手強い。英国の訴訟ではアップルがサムスンに謝罪する広告を掲載するという判決が下された。米国での訴訟も陪審員が中立的立場を守れなかったとして問題になっていることから、アップルの一方的な勝利で終わることはなさそうだ。
趙 章恩=(ITジャーナリスト)
日経パソコン
-Original column
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20121116/1070822/